先日、Xにて、下記のような投稿をしました。
「負ける」コンペあるあるです。
「勝つ」コンペあるあるではなく、「負ける」コンペあるあるです。
X上では文字数の関係上、説明不足気味なので、ブログにて解説します。
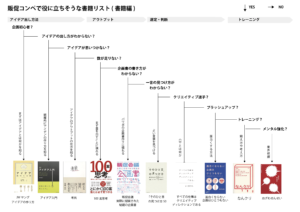
「負けるコンペあるある」とは?
負けるコンペあるあるとは、ひとやすみくんが業界経験をもとに体験的にまとめた、コンペで負けた時のあるあるです。(業界内の知人友人情報も参照)
独断と偏見によるあるあるなので、ジョークと思いつつ参考にしてください。
「負けるコンペのあるある」を知ると
勝つコンペあるあるも重要ですが、負けるコンペにも共通してあるあるは存在します。
負けるコンペのあるあるを知ることで、勝ちに繋げることができると思います。
負けが多い人は、逆に改善するポイントとして参考になります。
「負けるコンペあるある」解説
それぞれ「負ける」コンペあるあるを解説して行きます。
個人的にまとめた、あるあるなので、少し会社や業界によって異なる可能性があります。
1 良い提案にしようとする
コンペが始まると、皆、口を揃えて「良い提案にしよう!」といいます。
ただ、これは、一見良いように感じますが、トラップが多いです。
そもそも「良い提案」というものが定義されていない状況で、「良い提案」というものはできません。
ピッチリーダーが「良い提案」という曖昧な表現をした際は、その定義を確認しましょう。
よくある良い提案の例でいうと下記のものがあります。
- 広告賞を取れるような提案
- 自分たちが良いと思える提案
- 自分たちが面白いと思える提案
- 社会的に意義のある提案
ただこれらは、一見良いように見えますが、クライアントにとっては、関係のない「悪い提案」の時があります。
もちろん裏ミッションで、上記の内容を含んでいるのは結構です。
ただコンペで勝つということを念頭に置いた場合は、上記のものは「自己満足」の提案であり、「良い提案」とは異なるので注意が必要です。
2 社内絶賛される
これが一番厄介だったりします。
社内の偉い人などから絶賛された時は、「イエロカード」もしくは「レッドカード」です。
社内で絶賛されるということは、「過去の何かしらの事例に近しい」という状況になっています。
社内の偉い人はいわば、過去の人です。過去の人から良いといわれるということは、現代の時流に乗っていない可能性が大いにあります。
社内で確認して意見が割れて、反対意見が出るけど、それを論破できるロジックを準備するのが一番勝ちに近い方法です。
社内で絶賛 = イエローカード と認識しましょう。社内で絶賛されると気持ち良いですが、改めて提案内容を見つめ直した方が良いです。
「私は好きじゃないけど」「私はわからないけど」などと社内の人に言われたときは、逆に、鉱脈の可能性が秘めている時があります。
3 最後まで戦略に拘る
これも一見すると、正しいように感じます。
しかし、厄介です。戦略を最後まで拘るということは、最後まで戦略が定まっていないということを指します。そんな戦略は正直、正しくないものであることが多いです。正しい戦略は、自ずとすぐに出てきます。
そのような状況では、施策や企画は絶対にブレブレの状況になります。
戦略が最後まで粘ると、一貫性がない提案になります。これは、負けフラグが立ちます。
戦略が定まらないときは、せめてターゲットと訴求点を絞り、コミュニケーションを走り出させます。
広告領域に限っては、戦略はエグゼキューションからの逆算でも生み出すことができます。
むしろ広告領域の戦略は、戦略の仮説からエグゼキューションを考え、逆算的な戦略設計での検証の方が良い戦略に生まれることが高いです。
4 面白い企画になってる
これは、1の「良い提案にしようとする」と少し似ています。
「面白い企画」とはなんなのでしょうか?
人によりさまざまな解釈があります。
- ユニークな企画
- 新規性がある企画
- ファニーな企画
- 奇を衒った企画
- おかしい・笑える企画
面白い企画にはさまざまな企画があります。
ただ、これも「面白い」がクライアントのビジネスにどう紐づくのかを考える必要があります。
故に、自分が「面白い企画」と思ったものとクライアントが「面白い」と思う企画が必ずしも一緒であるとは限らない。
また、基本的に「面白い企画」というのは、どこかで自分が体験があるものが多いのでどこかしらに「既視感」が必ずあります。その既視感をうまく超える、もしくは、活用するということを考えた方が良いです。
面白い企画 = 何が面白いかの言語化 がこのトラップに勝つ方法です。
5 資料が早めに終わる
これも昨今、良いと思われていますが、なぜか資料が早めに終わった時のコンペは負ける可能性が高いです。
これの原因の一つに「こんなもんでいいか病」と「資料修正するのめんどくさい病」にかかっている可能性が高いです。
「こんなもんでいいか病」は、その名の通り、提案に対して自分の中でボーダーラインを決めて「こんなもんでいいか」という線引きを引いてしまう病です。この病の一番のポイントは、提案資料の一番伸び代がある提案前日の修正タイミングを捨ててしまうことです。
実は、提案資料で一番伸び代があるのは、提案前日~直前です。このタイミングに、資料は化学反応を起こしやすいです。営業、デザイナー、プランナー、CD、AD、外部、すべての人が完成資料を見た後は、それぞれに「意見」や「気づき」が絶対に発生します。提案資料は、完璧なものは存在しません。ゆえに、最後のチーム全体の化学反応が起こります。それを逃してしまうのは、コンペの敗因の大罪の一つになるのは、よくあることです。
うさぎと亀の話に近いです。
もう一つの病「資料修正するのめんどくさい病」は、最悪な病です。大御所やある程度慣れたプロや、忙しい若手などがいるときに発生する病です。この病は、人によるので難しいです。
資料を修正するのはめんどくさいのはわかります。ただ、資料を修正しないでコンペに負けるのが良いのか、資料を修正して少しでも勝つ確度を高くするのか、それは、当人の判断によるのでこの病は難しいです。
頑張って修正しても、負けるコンペはあるので、必ずしも「資料を修正する=正」ということも認識が必要です。
6 プレリハが何事もなく終わる
これも、一見良いように感じますが、危険信号です。
勝つコンペは基本的に「プレリハは荒れる」というのが鉄則です。
めんどくさいですが、プレリハはある程度、荒れるのが成功です。
ただ、厄介なことにプレリハで荒れることが良いと言いつつ、指摘されたことをただ修正すれば良いというわけではないということです。
指摘されたところを打ち返すためのロジックもしくは、企画があれば良いです。全部の指摘を鵜呑みに修正するのもまた負けへと繋がる一歩になります。
プレリハは、第三者意見を客観的に得る場と心得ると良いです。それは、クライアントも同様に感じるポイントであることが近いです。
反対意見を頷かせる、もしくは、納得させる提案にするためには、「プレリハが荒れる」というのはとてもいいことです。
反面教師的でもあり、本当に正しい時もあり、そこは判断が必要です。
7 こだわりが強い人がいる
これは、厄介なポイントです。
良いことではあるのですが「こだわり」が強い人がいると吉が出ることもあれば、凶が出ることがあります。
こだわりとは諸刃の剣で、それがうまく機能すれば良いのですが、大抵の場合は、「執着」に陥ることが多いです。
単純にいうと視野が狭く、博打になりかねないです。
また「こだわり」とコンペに勝つことはそこまで関連しないので、客観的に提案として良いか悪いかは判断すべきです。
基本的にコンペは時間的な制約が必ずあるので、一部にこだわるのは時間的に効率が悪い可能性があります。
例えるならば、受験問題で全問で6問ある中で、大問6だけをひたすら解いて他の大問1~5が時間がなくて解けないような感じです)
8 誰も反感がない満場一致
これも、提案上の罠の一つです。
勝つ提案で「満場一致」は絶対に存在しないです。
必ず誰かの意見は、捨てなければいけないです。
圧倒的にレベルの高い同レベルの人が揃っている場合であれば、満場一致になる可能性がありますが、大抵の場合はそんなことありません。
低いレベルで留まっている意見の一致か、同調圧力により意見が出ていない場合が多いです。
反感がない満場一致の場合は、チーム自体を改める必要があります。
9 負けても誰も困らない
これは少ないかもしれないですが、コンペに負けても実は誰も困らないという状況があったりします。
この場合は、正直、コンペ自体が博打になるので、そもそも勝ち負けというより「数」としてコンペになります。
このコンペの時によく「良い提案をしよう」に陥ることがあります。
これに関しては、正直、対策のしようがないです。
10 よいチームである
これも、トラップです。
良いチームであると、なぜかコンペに負けやすいです。
「このチーム素晴らしい」「居心地が良い」「メンバーが話しやすい」「◯◯さんがいるから安心」という状況は、実は、コンペにおいては負けフラグに近いです。
なぜならば、良いチームでは、それぞれが良い人だからです。
裏を返せば、信頼関係を崩すのが怖い状況ということです。このような状況下では、率直な客観的な意見はとても言いづらくなります。
結果として、なぁなぁな提案に落ちることがあります。
よいチームであるということと、コンペに勝つということはそこまでイコールではないということです。
勝つチームを作るために、ある程度、緊張感のある「ちょっと嫌だなぁ」っていう人をチームに入れるのもテクニックの一つになります。
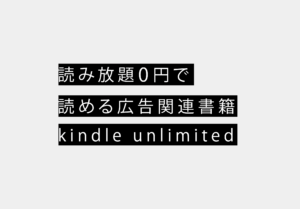
まとめ
今回は、コンペで負けるあるあるをまとめました。
個人的にまとめたものではありますが、「あるある」と頷けることはあるのではないでしょうか。
ただ最後に一言言うと、コンペに勝つと言うことが全てにおいて正しいという訳ではないということを認識するべきです。コンペに勝っても、人間関係が崩れたり、体調を崩したり、社内外の関係性が崩れたりしては元も子もないです。
コンペに勝つのも重要ですが、ほどほどに抑えることも重要です。時には、負ける勇気も必要です。
あるあると楽しんでいただければ幸いです。
参考になれば幸いです。この記事がよかったら何かしらリアクションくれると嬉しいです。
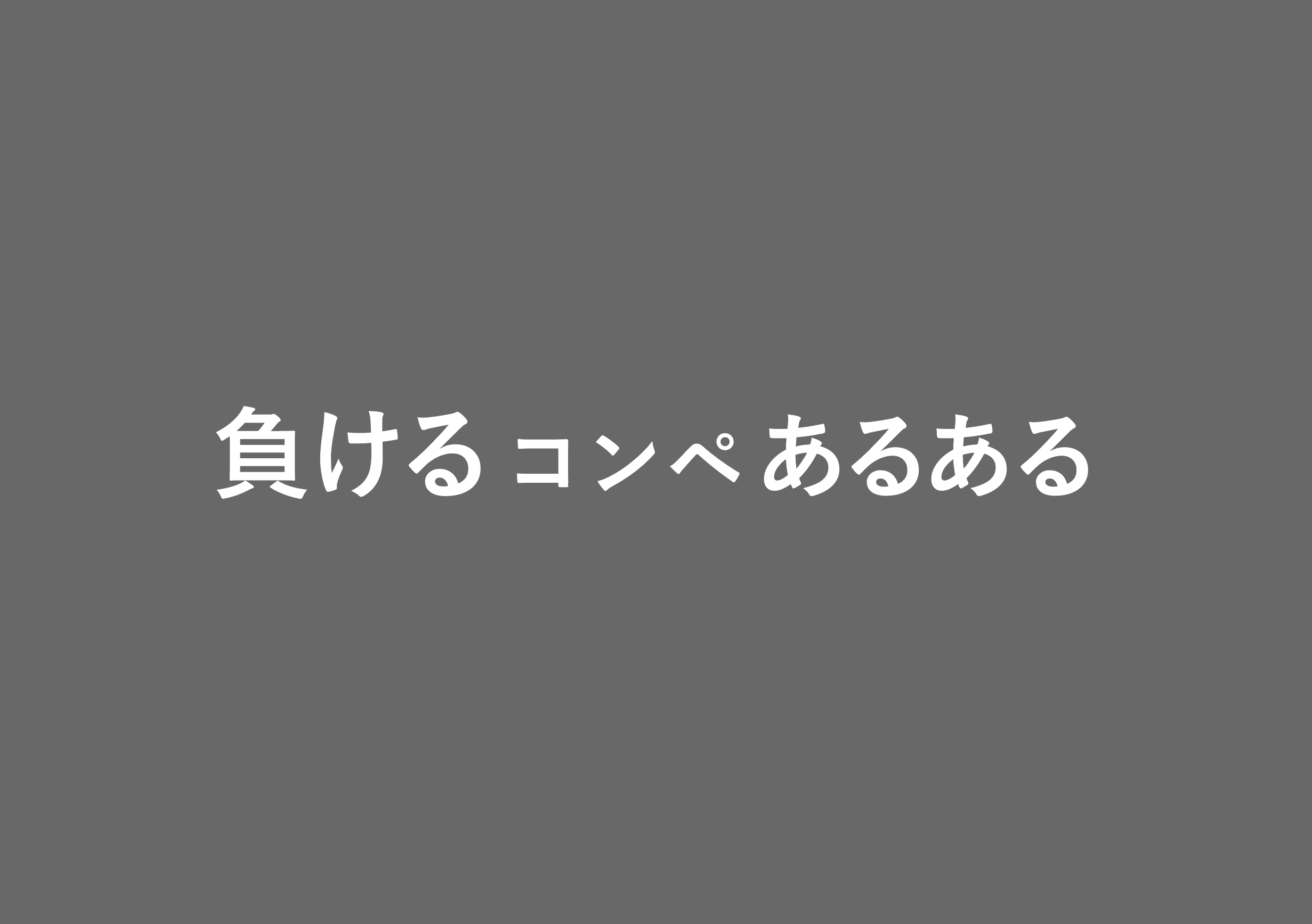
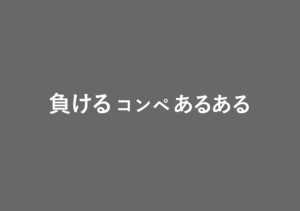
コメント